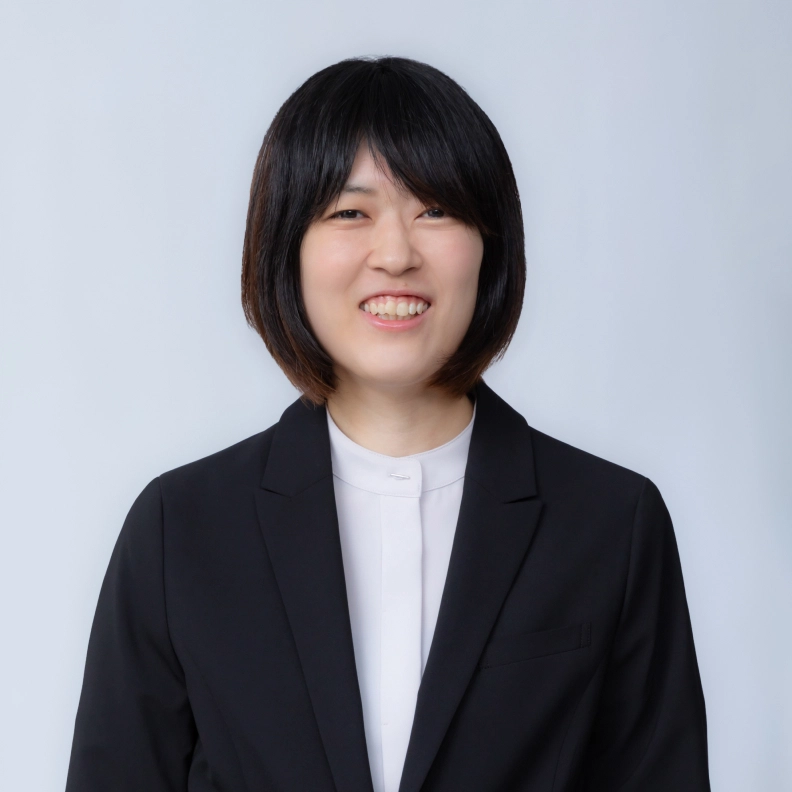安全を守り、信頼を育てる――。
整備士を率い、安定した工場運営を実現。
鶴見整備工場(セーフティークオリティ整備工場)工場長
石川 政志
2016年入社(中途)
東部ネットワークに入社した経緯を教えてください。
私は2級自動車整備士の学校を卒業後、大手自動車メーカーのディーラー勤務や、タンクローリーのトレーラーおよび産業廃棄物のトラックの乗務などを行っていました。直近ではロードサービスの会社で大型車の故障移動に携わっていたので、これまでの経験を活かした働き方ができることを期待し、東部ネットワークへ入社を決めました。
もともとは鶴見整備工場の整備士として採用されましたが、主に携わっていたのは受付等のサービスフロント業務です。また、私は大型や牽引などの各種運転免許を持っていたので、車両修理を行うにあたってトレーラーを工場の中に入れるといった移動も、私が担当していました。

工場長に就任されたのはいつ、どのようなきっかけだったのでしょうか?
ここの責任者になったのは2018年10月です。前任の工場長の退職が急遽決まり、私が後を任されることになったのです。正直なところ、それまで私には責任者としての経験がまったくなかったため不安もありました。ですが、会社がバックアップしてくれるとお話を受けたので、思い切って挑戦してみることにしました。
最初はドタバタで大変でしたが、現場のスタッフの協力もあり、一つひとつ乗り越えて、なんとかやってこられたと感じています。
鶴見整備工場の役割を簡単に教えてください。
この工場では、自社が保有する車両の整備を手がけています。当社が扱うような大型車両は1年に1回の車検が義務付けられており、車検のための整備業務を日々手掛けています。もちろん、日常的に起こりうる車両の不具合対応や点検業務も行っています。なお、こういった自社の整備仕事に加え、現在は、いすゞ自動車首都圏株式会社さんからも、一般修理および車検整備を一部お任せいただいている状況です。
現在この工場では、私のほかに事務員が2名、フロント係が2名、検査員兼整備士が6名、全体として11名で動いています。
石川さんの現在の仕事内容についても教えてください。
私の日常業務としては、現場から上がってくる伝票に関する金額や内容のチェックなど、事務的なものが中心です。また、私は「自動車検査員」の一員でもあるため、車検整備検査に関する書類の確認や、車検を受けた後に発行される保安基準適合証書の発行手続きといったことも、それらの権限を持つ人間として対応しています。
現在、私自身が整備を行うことはまずありませんが、責任者として品質維持のための現場の管理、そして何かトラブルが起きた際には指示や助言をするなど、常に工場全体を見ています。

業務日の大まかなスケジュールを教えてください。
毎日8時半に朝礼があり、そこで整備士たちに1日の流れ(作業内容の説明・段取り)と、2人1組で整備を行うためのメンバーの組み合わせを説明します。その後、メールチェックなどデスクワークを進めていく流れは毎日ほぼ同じですが、基本的に私の仕事は決まった時間で動くものはほとんどありません。
他にやっていることとしては、作業の遂行状況によってのスケジュール調整や、会社から求められている資料の提出、Webミーティングへの参加、そして車検関連の書類チェックなどを進めていきます。午後になると、だいたい翌日の仕事の段取り準備で、お客様への連絡や確認をとることが多いですね。
責任者としてのやりがいはどんなところにありますか?
工場長として、工場のことは私にすべてを任せていただいている形です。法令遵守は前提として、仕事の組み立て方など、私の裁量で進めることができるところは、やりがいを感じています。
もちろん、売上目標に到達するために、予め計画を立てて動いていくことが必要です。数字を意識しつつ、現場を見ながら無理のないように仕事を組み立てていくのは大変ではありますが、きちんと回っていくときは充実した気持ちになります。
逆に大変なこと、課題だと感じていることはありますか?
この業界では慢性的に整備士不足であり、もっと人手が増えたらいいとは思っています。特に大型車両の整備となると、なかなかハードルが高いと感じてしまう人もいるのかもしれません。
たしかに大型の場合、車体はもちろん各種部品一つとっても乗用車より大きいですし、危険が伴う作業がまったくないとは言えません。それでも、当社には大型車両の整備をやりたいという思いで入社した若手スタッフもいます。安心して働き続けてもらえるよう、安全管理や働きやすい環境づくりには十分に配慮していますので、少しでも興味を持っている方には、ぜひチャレンジしていただき、皆さんと一緒によりよい整備工場を作り上げていきたいと考えています。

整備士の「働きやすさ」の観点で工夫・配慮していることを教えていただけますか?
たとえば、夏場になると工場はかなり暑くなってしまうので、11時半頃から13時まで長めの昼休みをとってもらっています。あとは熱中症にならないよう、日頃からドリンクや塩分の入ったお菓子を配ったりもしています。
それ以外の場面でも都度スタッフの様子を確認し、業務がやや落ち着いているときは柔軟に休憩をとれるようにするなど、メリハリをつけながらも、なるべく疲労を溜めずに働けるように気をつけています。
東部ネットワークに入社してから、特に思い出深かった出来事はありますか?
先ほど、私たちは民間整備工場として、いすゞ自動車首都圏株式会社さんの整備業務も担当しているとお話しました。いすゞさんから安定してお仕事をいただけるようになるために、何度もお客様の元へ足を運んで、一から信頼関係を築き上げていった思い出は印象に残っていますね。
現在はやりきれないくらいお仕事のご依頼をいただいているので、いすゞさんにとって重要な外注先として認めていただけているのかなと思います。それが工場の売上にもつながっていますから、私たちにとって非常に大事なお客様です。
信頼関係を築くのには時間がかかります。反面、それを失うのは一瞬なので、工場一丸となって一つひとつの作業を丁寧に進め、質の高い仕事ができるように努力してきました。もちろん、何か少しでもご迷惑をかけてしまった場合には誠実に謝罪をする。そうやって当たり前のことを当たり前にやる、そんな大切さを実感する出来事でした。
仕事をする上で大切にしていること、心がけていることはありますか?
この工場での業務は安全や信頼に直結するものなので、あらゆる業務において気を配っています。特に自社の車両は、「なるべく仕事に穴をあけないように」という点を重視して仕事を進めていきます。翌日の輸送が決まっているのに急な不具合が出てしまった場合には、みんなで協力し、何とか走れるように作業していくこともあります。仕事は荷主様ありきで動いていきますから、もし車両が故障して動けないとなってしまえば、自社の損失になるのはもちろん、お客様にも多大なご迷惑をおかけしてしまいます。路上故障を起こさないよう、常に細心の注意を払って作業を進めています。
私個人としては、どれだけ忙しい中でも駄目なものは駄目という姿勢で、妥協はしないことを心がけています。最近は世間でも、不正車検の話題が取り上げられることも多いですが、管理者としては、「とにかく判断を間違えないように」ということに、最も気をつけています。
検査時、どうしても判断が難しい場合には神奈川運輸支局にまで車を持ち込んで、国の検査機関で検査をすることもあります。「これくらい大丈夫だろう」と思い込んでしまったり、曖昧なまま車検を通してしまったりしたら、後から重大な問題になりかねません。そういう判断もすべて私がしますので、いかなる場面でも不正を起こさないように気をつけています。
オフの時間はどのようにお過ごしですか?
私の業務はそこまで肉体労働でもありませんので、休みは身体を休めるというよりも、積極的に外に出かけています。釣りが好きで、月に1~2回は、以前タンクローリーに乗っていたときの仕事仲間たちと一緒に釣りを楽しんでいます。だいたいはアクアラインを渡って千葉のほうまで行き、船に乗っています。
最後に、就職・転職を考えている方に向けてメッセージをお願いします。
この工場では、皆で協力しながら物事を乗り越えていく姿勢で業務を進めています。できれば大型を経験している人、2級整備士資格を持っている人が望ましいのは確かですが、現在働いているスタッフの入社時点でのキャリアはまちまちです。経験が浅くても、しっかりと指導しますのでご安心ください。
もし検査員資格を持っていれば検査業務もお任せしていきたいですし、オールマイティーにいろんなことをやれる環境です。整備士としてとてもやりがいを感じていただけると思いますので、大型整備に挑戦したい方がいたら、ぜひ積極的に応募いただきたいと思っています。